企業会計において「減損」という言葉を耳にすることは少なくありません。特に固定資産を多く保有している企業にとって、減損検討は決算上の重要なプロセスです。この記事では、減損の基本から検討の流れ、実務での注意点まで解説します。
減損とは何か?
「減損」とは、企業が保有する固定資産(建物、機械設備、無形資産など)の価値が大きく下落し、将来得られると見込まれるキャッシュ・フローで回収できない状態になった場合に、その資産の帳簿価額を回収可能価額まで引き下げる会計処理を指します。
つまり、資産の価値が下がったのに帳簿価額が据え置かれるのを防ぐための仕組みです。
減損検討が必要となるきっかけ
減損の可能性を検討するきっかけ(トリガー)は、会計基準上もいくつか例示されています。代表的なものは以下の通りです。
- 市場価格の大幅な下落
- 資産の稼働率の低下や休止
- 経営方針の変更(事業撤退、使用目的変更など)
- 技術の進歩による設備の陳腐化
- 赤字の継続などによる将来キャッシュ・フローの悪化
これらの兆候が見られたときに、**「減損の検討が必要かどうか」**を判断します。
減損検討の実務プロセス
実際に減損の可能性がある場合、企業は次のような流れで検討を進めます。
- 減損兆候の有無を確認
決算時や四半期ごとにチェック。 - 資産グルーピングの判定
単独資産ではなく、キャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングします。 - 将来キャッシュ・フローの見積り
グループごとに将来得られるキャッシュ・フローを合理的に見積ります。 - 回収可能価額の算定
- 使用価値(将来キャッシュ・フローの割引現在価値)
- 正味売却価額(処分した場合に得られる金額から処分コストを引いた額)
のいずれか高い方を採用。
- 帳簿価額との比較
帳簿価額が回収可能価額を上回っていれば、その差額を「減損損失」として計上。
減損検討における注意点
- 過度な楽観は避ける:将来キャッシュ・フローの見積りは恣意性が入りやすいため、客観性が重要。
- 税務との違いに注意:会計上は減損処理が必要でも、税務上は損金算入が認められないケースがあります。
- 開示義務の対応:有価証券報告書や決算短信で減損の内容を開示する必要があるため、説明可能な根拠を準備しておくことが重要です。
まとめ
減損検討は、単なる形式的な手続きではなく、企業の財務状況を正しく示すための重要な会計プロセスです。
特に固定資産や投資が大きい企業にとっては、業績へのインパクトも大きくなるため、
兆候を早期に把握し、適切なプロセスで検討を進めることが求められます。

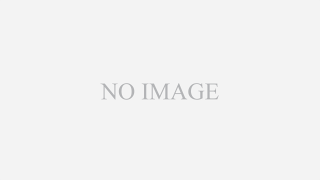
コメント